お父さん、ありがとう
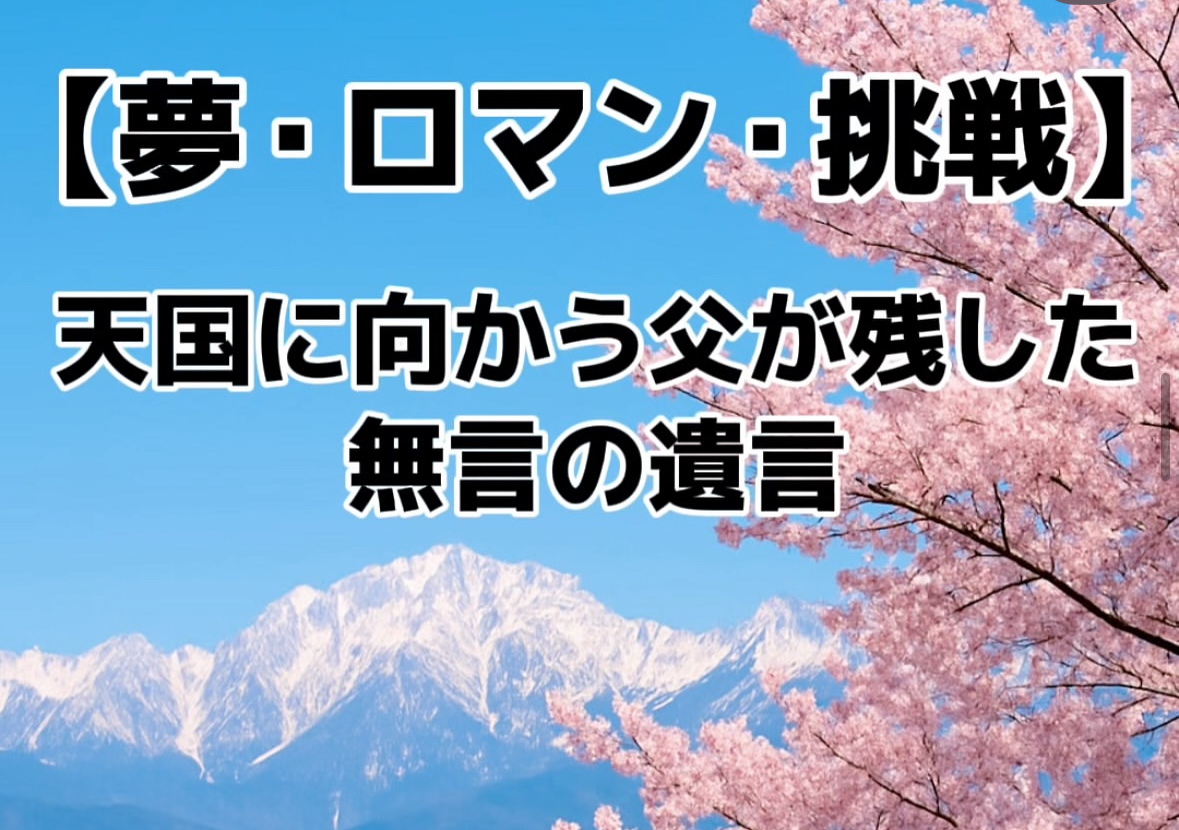
信じられない、信じたくない。
受け入れられない、夢であってほしい、いや夢ならすぐに覚めてほしい。
先日、父が永眠しました。
海上自衛隊上がりで教師歴32年、引退後も学校や施設でボランティアを続けながら、毎年、水泳大会では年齢記録を更新し続けた不死身の父が永い眠りにつきました。
多趣味でありがなら、何をやってもピカイチ、特許2件、たった一人での石垣づくり、小説を書けば連続受賞、DIYはログハウス、ハーモニカ演奏の歌声サロンでは高齢者の涙を誘う人気講師に。ハンターでもあり、猟犬30匹以上を飼育する名ブリーダー。父が育てる猟犬は専門雑誌で紹介され、泥棒にあうのが通例なほど。毎日、大きな窯でブロイラーからもらってくる廃材を調理。庭は動物園のようなおりがズラリと並び。土地を買ったら公園をつくり。戦国武将のように、徐々に領土を広げていく。
もともと商業高校だった女子高で化学を教えていた父。
化学を真面目に勉強したい生徒さんはどれだけいたことだろうか。
不人気教科No1、役に立たないと思われる授業で、父の口癖は「生徒が点数を取れないのは教え方が悪いからだ」と言い、在任32年の間で一度も赤点を出さなかった。「(生徒が)できるまで追試をする」と言って、何度も何度も手を変え品を変え生徒に接していた。今ではそんなことはあり得ないが、当時は、毎日のように家に電話がかかってきていて、丁寧に対応していた。
不人気な化学を教えつつも、人気投票では毎年No1、体育祭では恒例の仮装大会で注目を浴びた(浴びさせられていた)。週末には学校の先生方が神妙な面持ちで相談にやって来て、変えることには笑顔になっている。
「人を押しのけて上にあがってはならぬ。弱いもの、若いものに手を差し出して引きあげろ」とよく言っていたようだが、まさに有言実行。人生を通して裏表なく、信念を貫き淡々と生きた父。
毎日の犬の散歩は山中を駆け巡り、心身ともに強かった父。
身も心も強靭だった父に転機が訪れる。77歳の時に前立腺癌が発覚。
ショックを受けた家族に「見つかって良かった」、「運が良い」と笑顔で言い切った。
父は手術での完全復帰を望むも、主治医は高齢を理由に手術を否定。
その後、主治医が変わり、父の体力と気持ちの強さから、手術に踏み切る。
手術室から部屋にベッドで運ばれる最中、看護師さんらに「皆さん、お元気ですか?」、「今日も元気に、笑顔で楽しく頑張りましょう」と場を和ませた。
そして、翌年も水泳大会で記録を更新。
「100歳まで生きる」と日々元気に暮らしていた。
ところが、その翌年、突如の大病が父を襲う。
ANCA関連血管炎(膠原病の一種)、聞いたこともない、原因が分からなければ治療方法もない難病。微小血管に炎症が起きて、腎臓と肺の機能があっという間に著しく低下、みるみる様態が悪化し、呼吸困難、ひん死の重体に陥った。
今にも息が途絶えそうな中、細々とした声で「(気管切開を)早くしてくれ」と言い、主治医からは「最後の会話をしてください」と言われて、家族全員で泣き崩れながら、父を励ました。妊娠7か月の妻も一緒にいた。子どもは父の生まれ変わりであるかのように思えた。父が声を振り絞って妻に伝えた「子どもの名前は平仮名にできないかな」と。当時考えていた漢字を良く思わなかったらしい。遺言のようにも聞こえ、その場で即決、娘の名前を平仮名にすると伝えた。
主治医からは、「かなり難しい状況」、「この状況で退院できた例はない」と言われたが、かろうじて、本当に危機一髪で父は命をつないだ。それでも厳しい状況が続いたが、そこから奇跡の復活劇が始まる。意識が戻ると、集中治療室で「喉がカラカラだ、水をくれ」と手で合図を送るようになった。そうしてやりたいが、人工呼吸器がついているので、そうすることはできない。
長い長い(と感じる)日々だった。またANCAの症状が出たら体力は持たない。父と医療スタッフを信じるしかなかった。それでも、気力に満ちた父の様子は少しずつ改善され、人工呼吸器がとれて一般病棟に移された。
直に会話ができるようになったが、父の涙を初めて見ることになる。
幼少の頃から「男は泣くな」と言われ続けた。父の実の父である祖父の葬儀の時でさえ、歯をかみしめ拳を握りしめながらも涙を見せなかった父が、思わぬ時期で死を感じて「体を鍛えていたのに悔しい」と嗚咽をもらして号泣した。
そんな父を見て、私もある挑戦を決意した。
医学の博士号と取ることだ。通常の仕事に加えて、必死で2つ目の学位取得を目指した。それを父に話すと、とても喜んでくれた。(仲間たち、共同研究者らの力を借りて、この2年後に医学博士を取得することができた)
2か月ほど経過すると、父の体はあっという間に細くなり、弱り切った体ながらリハビリができるようになった。
その頃には、呉、江田島での自衛隊時代を顧みて、「もみじ饅頭が食べたい」、「海軍カレーが食べたい」と言い出した。すぐに広島に住む親せきが、食べきれないほど持って来てくれた。
ある時、私の携帯にメッセージが届いた。
「わが夢を 捨ててたまるか 若櫻」
自分のことを若櫻とし、新たなる挑戦を始めていた。
「まだまだ自分は若造だ、100まで生きる」
「小説の続きは考えておる、すぐに再開する」といい、病室で執筆活動を始めた。
2か月間寝たきりで、身は細り果ててしまった。
自慢の体が動かなくなっていることにショックを受けたが、猛烈な自主リハビリを開始した。何度も転んで、体中が紫色のあざだらけに。遂には頭も強打して腫れあがった。医師らに止められても止められても決して自主リハビリを止めなかった。
時折、「おーい、頑張ってるぞー、お前も頑張れよ」などとおちゃめなメッセージが来た。
やはり、父は不死身だった。みるみる内に筋力と体力が回復していった。
「この状況で退院できた例はない」と言われた父が、たった3ヵ月で退院することになった。主治医は「奇跡」だと言った。
しかし、もちろん、元の体ではない、杖をついてのヨチヨチ歩き、週3回の透析、そして、強力なステロイドの服用。この薬でANCAを抑え込む以外に父の命を守ることはできない。ただし、強力なステロイドは免疫力を弱めるため、細菌やウイルスに感染しやすく、毒性が弱くても重度の症状を引き起こす可能性が高い。
そこへ、新型コロナがやってきた。
実は、母も「非結核性抗酸菌症」という肺の病気が発症し呼吸が苦しくなった。しかも、転倒して大腿骨を骨折。肺炎を起こし40℃の熱の中で緊急手術をした。母も名医に命を救ってもらい、半年間の入院生活を経て、家に戻り父との老々介護がスタート。
両親ともに、高齢者+重篤な基礎疾患、猛烈にコロナを恐れた。
マスク、手洗い、人の出入り、郵便物のスプレー消毒など、コロナアウトブレイクから今日まで、綿密に続けてきた。私たちもほとんど帰省することができなかった。幸い独立して、テレワークがほとんどの私だ。必要な時は私一人で帰って、せっせと働いて帰った。孫との交流をしてもらいたかったので、強制的にLINEの動画チャットを覚えてもらった。
そして、もう一度、病院や施設でハーモニカで童謡を奏でて、皆さんに歌ってもらうボランティアをオンラインでして欲しかった。しかし、通っていた施設は全て、オンラインの対応ができずに、結局実現することはできなかった。
しかし、ものすごく良いこともあった。またしても奇跡が起こった。
週3回の透析から解放されたことだ。弱弱しくも、父は再び、小説を書き、畑を耕し、ものづくりを楽しめるようになった。
その後、父は何度か肺炎にかかり、入退院を繰り返す。
電話が鳴る度に恐怖を感じた。それでも、父は生き延びた。
強い、本当に強い人だ、私を含む親戚中の誰もが感心した。
そして、父はやはり不死身だと皆が思いこんだ。
ANCAで退院した当時、世界中のデータ(論文)を集めてみたが、70歳前半での場合、5年生存率は20%ほどであった。父の年齢でのデータはなく、心が折れそうな気持だった。しかし、父は入退院を繰り返しながらも7年間、最愛の母との暮らしを続けてきた。細々と弱弱しい二人が寄り添っている姿は、いつも涙がでるほど愛情と優しさ、そしてまごころに満ち溢れていた。
昨年夏、庭仕事をしていて転倒。
起き上がることができない。大声で助けを求めるも、難聴の母には父の声は届かない。
熱中症になりかけながら、助けを呼び続ける。
実家はかなりの田舎、山の麓で隣人とも離れていて、誰にも声が届かず数時間が経過。
日が暮れて、父の体力も低下していく。
そこに、偶然、近くを通った人が、かすかな声に気付いて、夫婦で救助。
フラフラになった父の服を脱がせ、水をかける。またも助かった。
9月に一人で帰省した時には、一緒に郵便局に行ったり、買い物に行くことができた。2人の孫と妻にも大きな綿あめを買ってもたせてくれた。
子ども達と両親を合わせたかったが、正月はインフルエンザの流行が続き、帰省できず。
そして、2月末。夜中にベッドから落ちて、またも立ち上がることができず。
熱もあったので、救急車で運ばれてそのまま主治医のいる病院へ入院。軽い気管支炎だったので、命に別状はなかった。主治医の病院のベッド数が足りず、リハビリ病院に転院。
またしても、鬼の自主リハビリが始まった。しかし、ますます弱った体だ、またも転倒が続く。
それでも、「病院にいるのだから」と、私たち家族は安心もした。父の早期退院を疑う人は誰もいなかった。
これまで何度も入院する度に、父と病院の先生、スタッフ宛に手紙を書いてきた。
しかし、この頃、独立後最大のピークを迎えていた。
両親はいつも私のことを応援してくれて、どんな小さな成功でも大いに喜んでくれた。だから、必死で働いた。睡眠時間を惜しんで働いいた、家族を犠牲にして働いた。
同時に、大切な両親への手紙を書く時間までを惜しんて働き続けてしまった。
「4月になれば落ち着くから、待っててね」
心を鬼にして働いた。大きな間違いを犯してしまった。カレンダーと机の上のメモに、「父への手紙」と書いてある。優先順位を間違ってしまった、生涯心残りだ。
リハビリ病院に入院して3週間、3月21日。
妹から、父が新型コロナに感染したと連絡があった。
あれだけ気を付けていたコロナ、あんなに恐れていたコロナ。
病院にいるから安心と思ったが、忘れた頃に新型コロナに院内感染。
父はどれだけショックを受けたことだろうか、心が苦しく胸が張り裂けそうだった。
「お願い、ワクチンよ、効いてくれ」
「頼む、薬よ、効いてくれ」
家族全員で祈りに祈った。
翌日、土曜日の昼時、オンラインで講座をしている時に、LINEが流れるのが見えた。
「キトク」という文字がチラリと見えた。
90分の講座、残り時間は60分、長い長い60分だった。
生徒に申し訳なかったが、心が折れそうで講座に集中できなかった。
いつもは時間オーバーが普通で、満足してくれるまで講座を続けているが、この日は90分ちょうどで終わらせてもらい、恐る恐るLINEを開いた。
医師である義弟からの連絡で、やはり父が危篤状態とのこと。
病院の方からは、様態が急変し手の打ちようがないとのことだったが、義弟の懸命の懇願で、ANCAの主治医がいる病院に緊急転送してもらうことになった。この日は土曜日だったが、幸運なことに主治医の先生が当直でいてくれた。父の名前を見かけた主治医の先生は、父が搬送されている間にも処置の準備を進めてくれた。父が到着した時は、全身が痙攣し、血中酸素濃度は50%を切っていた。
直ちに、酸素吸入、輸血、透析、薬剤投与など考えられる全ての処置をしてくれたが、父の危篤状態は続く。一刻の予断も許さない状態が続いた。
講座を終え、大至急準備をして、妻と二人の子どもと一緒に病院に向かった。どうしても、車のスピードが上がる。福岡までの道はいつもよりも長く感じた。
集中治療室へ向った。ガラス越しに時折痙攣しながら静かに横たわっている父の姿があった。
モニターで心拍数、血中酸素濃度などを確認し、胸が動いているのが分かって少しだけ安心した。それでも、いつどうなるのか分からない。
弱った母も緊張と涙で震えていた。
母の肩を寄せて、一緒に泣くことしかできなかった。
ガラス越しの父に話しかけても何の反応もない。
集中治療室なので、長居はできない、どうすることもできず、動揺しながら実家に戻った。
3月25日~28日には大阪出張が決まっていた。
独立後、初めての出張、初めての学会発表だ。
生徒の頑張りで研究が進み、中学1年生にして、業界最大の学会で発表することになっていた。半年間に渡る生徒との準備、もちろん、父も楽しみにしていた。
このまま父が命を落とせば学会には行けず、生徒だけで行かなくてはならない。
もしも、父の状態が維持できれば、、、どうするべきか、、悩みに悩んだ。
何度も心の中の父に問い続けた。
「最後までやり切れ」
何度聞いても、心の中の父はそう語った。
フライト当日、ギリギリまで悩んだが、いざとなれば大分から車で福岡に向かうよりも大阪から福岡に飛行機で戻る方が早いこともあり、大阪行きを決意した。
そして、翌日、中学1年生の生徒は見事な発表、見事な質疑応答を行い、大絶賛を受けた。
有名大学の教授らから、「是非ウチの研究室に来て欲しい」との声ももらった。
その間も、父は命ギリギリの戦いをしていたが、主治医によると、主治医の声に反応しているかもしれないとのことだった。うまく行けば翌週には一般病棟に戻れるかもしれない。父は懸命に生きようとしている。ただし、血小板値が戻らないので、脳や消化器官に出血があれば命は厳しい。
私も父の想いに応えるべく、残り2日間の予定をこなして、大分に戻った。
いずれにしても、その翌日はもう一度、福岡の父と母に会いに行く予定だったので、子どもを寝かしつけた後に、帰省の準備をして床についた。深夜1時くらいだったと思う。
翌朝、3月29日、またしても土曜日。
福岡に戻る支度をしている最中に妹から電話が鳴った。
「朝早くに妹から?」、悪い予感がした。
妹は泣いていた。
父はまだ生きている。心臓は動いている。
ただ、早朝に脳出血が起きて、瞳孔が開いている、、妹は泣き続けた。
父は脳死の状態だった。もう回復の見込みはないとのことで、輸血、透析、酸素吸入も徐々に減らしていくということだった。つまり、完全なる死を待つのみという状態だ。
動揺した、本当に心の奥深くから動揺した。
父は、私が学会から戻ってきて床に就くまで待っててくれていた。
拭いても拭いても涙が止まらなかった。
福岡に向かう車中、時折、大声で泣き叫んだ。
ただ、心配なのが母。母はまだこの事実を知らない。
父が危篤状態に陥ってから、事実を知らせるのは私の役割だった。
母は心配性で、体も強くない。
だから、事実をボカシながら時間をかけて説明してきた。
父は脳死の状態、、これを伝える勇気はなかった。
自宅に到着するまでに涙を乾かせて、笑顔で母に話しかけた。
私「お母さんも一緒に行く?」
母「昨日行ったから、今日は休もうかな」
私「もしも、もしもだよ、このままお父さんが亡くなったら後悔するかもしれないし、せっかく帰ってきたから一緒にいかない」
母「じゃー、行ってみようかな」
この日は、叔母さん(父の妹)と従妹も広島から来てくれた。
翌々日におばさんが入院するので、その日しかないとのことで、駆け付けてくれていた。もちろん、この二人にも事実は知らせていないし、知らせる勇気はなかった。
この日は、ガラス越しではなく、直接会うことが許された。新型コロナの感染リスクはないので、父に触ることも許された。
ICUに入ると、静かに父が横たわっていた。
前と同じように、静かに息をしていた。
もう痙攣はしてないので、その分楽そうに見えたが、軽く開いた瞼から見える、目の色はいつもの父とは違い、魂がゆらゆらしているように思えた。瞳孔が開いている目と人体だ。
母と二人で父の手を握りしめ、何度も話しかけた。
母は事実を知らないまま、父の復活を信じて話しかけた。
その様子を窓越しから親戚が見ていたが、父がもう戻ってくることはないと知る私の瞳からは次々に涙が零れ流れ落ちた。
「お父さん、お父さん」、「お父さん、お父さん」
次第に、「お父さん、ありがとう」を繰り返していた。
看護師さんが「お父さん、聞こえているので話しかけてください」と言ってくれたので、耳元に近づいて、「お父さん、ありがとう」と何度も話しかけた。
母がそれをどのように思ったのかは分からないが、次第に、感情が全面に出てしまい、声は大きくなった。
そして、父との約束事の確認をした。
「お父さんと約束したことは全て守るから安心して」
「25歳の時、当時人生で一番辛かった時に、お父さんが部屋の前に残してくれたメモ、覚えている?」
「"人生は試練の繰り返しであるが、それを如何に乗り越えるかで 人の価値は決まる"って書いてくれたよね。その時は辛すぎて、その意味を感じることはできなかったけど、その後は少しずつ試練がある度に、今自分は成長しているって、思えるようになったよ。だから、どんな試練だって乗り越えられる。お父さん、いつも温かく見守ってくれてありがとう、育ててくれて本当にありがとう」
そう話した後に、父の両目の目じりから涙が零れ落ちた。しばらく流れ続けた。
「お母さん、お父さん聞いているよ、お父さんに通じているよ、通じているよ」
より一層、感極まって号泣しながら、お父さんに感謝の言葉を伝えた。
1時間くらい経って、54年間連れ添い、「父の為に生きる」と言って生きてきた母を残して、親戚と交代した。
父の妹である叔母さんも「兄さん、兄さん、私だよ。元気だしんさい」、「兄さん頑張れ、兄さん頑張れ」と自らも病を患っているのに、外にもはっきり聞こえるくらいの声で必死で励ましてくれた。何度となく「兄さん頑張れ」と繰り返していると、また父の目じりから涙が零れ落ちた。母はただ「お父さん、、」と繰り返して泣いていた。
広島で看護師をしている従妹の姉ちゃんも「おじさん、本当にたくさんかわいがってくれてありがとう」、「また来るから頑張って」と手を握ったり、優しく胸を撫でたりしてくれた。
結局、集中治療室で2時間半ほど父との時間を過ごさせてもらった。
これは明らかに特別な状況です。最後のお別れをしてくださいということだった。
もう治療は終了。あとは、父の最後の生命力で心臓を動かすだけ。
看護師さんから「色んな家族をみてきましたが、本当に温かいご家族ですね、明日はどなたか来られますか?」と聞かれ、泣きながらもとっさに「まだ予定は決まっていません」と返答した。連日伺うと母が心配すると思ったから。
以前からその翌々日の3月31日に、上記学会のテレビ取材が決まっていた。
なので、またしても取材を受けに大分に戻るか、このまま福岡に留まるかの判断をしなくてはいけなかった。母のことも心身ともに心配だったので、連日父を訪ねるのはどうかと思った。それに、やはり父は「最後までやり切れ」というに違いない。母と夕食を済ませ、その日の晩に大分に戻った。
3月30日(日)、この日も朝4時に目が覚めて、ヒヤヒヤしながら、時折、呆然としながらも必死で仕事をした。積もった仕事リストを見ると、あっという間に時間が過ぎていく。夜になって、妹とLINEで話すと、この日、まだお見舞いにこれてなかった2番目の孫(妹の次男)が父に会いに行ってくれたとのこと。大学が忙しいから、まだ父のことを伝えていなかったけど、甥っ子は、可愛がってくれたじーじの事を知り、一目散に県外から駆けつけてくれた。甥はガラス越しの面会しかできず、必死で「じーじ、頑張れ」と繰り返した。すると、なんと、父はうなずいたというのです。それも4回。
妹と私は、父とまだ会話ができていると信じた、奇跡を願いたかったのかもしれない。
しかし、もう昨日までされていた処置はなされていない、父の自力だけに任されている、、、これで良いのか、悩んだ、頭がおかしくなるほど悩みに悩んだ。
ずっと前、父がスーパーマン並みに元気だった頃、父は言った、「俺が脳死になっても、生命維持装置は外すな。医療技術が発展しているから、何が起こるか分からない」と。それを思い出して、私は妹に、「やれることは全てやろう、もう一度主治医の先生に話してみる」と言い、日曜日の21時頃に病院に電話をかけた。
もちろん、主治医の先生は不在だが、集中治療室の看護師さんが主治医に電話をかけてくれて、「治療を再開して欲しい」という、私たちの無謀で身勝手な意図を伝えてくれた。すると、少し経ってから、看護師さんから電話がかかり、「明日9時に先生に電話をかけて相談してください」と言われました。少しほっとした気がした。翌日の取材のために部屋を片付けて床に就いた。
3月31日、取材当日の朝。
だいぶ疲れが溜まっていたのか、珍しくぐっすり眠りました。朝7時過ぎ、妻が寝室に近づいてくるのが分かった。ゆっくり戸が開いて、「よっちゃん」と言った瞬間に、何が起こったのか分かりました。「お父さんが、、」と泣き崩れる妻を抱きしめた。事実を避けたい気持ちで。それ以外は考えることができなかった。
父の最後を。最良の伴侶と共に見届けてくれた妹からのLINEには「今朝早くにお父さん、天国に旅立ちました。とても安らかな顔をしています」と書かれていた。次から次にどんどん涙が溢れでてきた。鼻からも、口からも、むせ返り、「お父さん」という声にもならず、倒れ崩れた。7歳と3歳の娘たちが、背中をさすってくれていた。
当時9時の主治医との話し合いを待たずして父は旅立った。
「もう、良い」、「大丈夫だ」、「先に天国に行って待ってる」という父のゆっくりと座った声が聞こえたように思えた。
取材はどうする?
父は繰り返すに違いない、「最後までやり抜け」と。
父は、最後に大きな試練と成長のチャンスを残してくれた。
準備してくれた生徒とテレビ局の皆様、いつも支えてくれる皆様の為にしっかりしないと。
前日事情を話したテレビ局の方には、到着後すぐに父のことが分かった(自分から話したのか、聞かれて答えたのかは思い出せない)。悲しみに寄り添ってくれたが、お互いに「絶対成功させよう」という雰囲気が流れた。
その後のことはほとんど覚えていないが、テレビカメラを前にイキイキと対応している生徒の姿を見て嬉しかった。
取材が終わると、すぐに福岡に車を飛ばした。私はとても運転できる状態ではなく、妻も肩をゆすりながらハンドルを握っていた。まだ小さな子ども達も不安な様子で後部座席に大人しく座っていた。いつになく高速道路が渋滞してて、不憫に思えた。
実家に到着する頃までには、父は葬儀場に送られていたが、閉店時間に間に合わず父に会うことはできなかった。父が亡くなった病院から送られる際には、主治医の先生がわざわざ見送りにきてくれたと聞いた。最後まで本当に温かい主治医だった。父のこと、家族のことを理解してくれる名医という他ない。
翌朝、一番に父に会いに行った。横たわっている父はもう動いていない。触っても抱きしめてもなんの反応もない。そして、もう温かみはなく冷たくもあった。「お父さん、お父さん」と何度叫んでも、自分の声が室内に響くだけ。お父さんとの時間はあっという間に過ぎた。
そして納棺。納棺師とともに、父を持ち上げて棺に運んだ。スローモーションのように、父が棺に入って行く。そして、納棺が閉じられる前に、もう一度、父の頬をなで、手を握った。納棺が閉じられると、いよいよ父が返らぬ人となった実感が増す、いたたまれない想いで全身の力が抜けた。
しかし、喪主としてやることがたくさんあった。といっても、前日に、妹夫婦が段取りをしてくれていたので、順調に進んだ。遺影の写真は、父が元気だったころ、東京での授賞式で母と私と一緒に撮ったものを選んだ。背景は、海上自衛隊あがりの海の男なので、海をイメージする水色のデザインにしてもらった。3時間ほどの打ち合わせを終えて、もう一度、父に「すぐ戻って来るから待ってて」と話しかけて実家に戻った。お通夜はこの日の17時からだったので、急いで身支度をして、父の思い出の品々を家中、庭中、倉庫の中をあさり集めまくった。父が書いた家訓の盾、海上自衛隊の標語「海軍五省」、狩猟、童謡、園芸、戦艦の本、釣り竿とリール、教師時代に修学旅行のオーストラリアで手に入れたカウボーイハット、愛する母との写真など。全てのアルバムを開き、数々の想い出の写真をアルバムからはぎ取った。部屋中に思い出が溢れかえり、涙も部屋中に飛び散った。父が大切にしていた犬に関するもの、手作りの本格的なゴム銃など、見つからないものもあった。「お父さん、ごめん」、しかし、もう時間がなかった。
母、妻、子どもを連れて、葬儀場に向かい、父と再会。母も妻も「お父さん、お父さん」と泣き崩れた。以前ひいおじいちゃんを亡くした経験がある上の子は、悲しさと得体のしれない雰囲気にのまれていた。下の子は、無邪気に棺の中の父をのぞき込み、「じーじ、ねんねしている」、「じーじは起きないの?」と言い、父に話し続けた。
棺の上、テーブルの上に、父の遺品や想い出の写真を飾り付けた。「あれを持ってくれば良かった、これも持ってくれば良かった」、「ごめん、お父さん」と後悔ばかり。
葬儀は家族葬、母、そして私と妹の2家族だけで行う予定で、誰にも知らせていなかった。唯一、ずっと父のことを気にかけてくれて連絡を取り合っていた、危篤の父の見舞いに来てくれた従妹だけに知らせた。すると、そこから広がり、その日の内に父の兄弟姉妹、全ての家族の甥っ子、姪っ子達が続々と駆け付けてくれた。「どれだけお世話になったか分からない」、「本当に素晴らしい人だった」、「いつも頼りになる兄さんだった」、「たくさん遊んでくれて感謝してもしきれない」、温かい言葉が身に染みると同時に悲しみも増した。急遽、式場を貸し切って、親族一同泊まることになった。どこからか聞きつけた人々も弔問にきてくれた。
お通夜では、下の子が棺の前に飛び出しておどけたり、お経を読む真似をしたりして、場が和んだ。喪主の挨拶は何を言ったのか覚えていないが、父のことを話して感謝の気持ちを述べたと思う。
そして、夜通しで父とのお別れの時間を過ごした。来てくれた親族から、色んな話を聞いた。父は決して自身の自慢話をする人ではなかったので、知らないことをたくさん教えてもらった。「努力の人」は父の代名詞のようであるが、子どもの頃からそうであったこと、天才的な一面や、逆に全くできなかったことも教わった。とりわけ、子どもの頃、吃音が激しくて、言いたいことを上手く言えなかったそうで驚いた。養成場に行っても治らなかったので、独自の方法を探し、ついに、「街に出て、何度も"知っている道"を聞く」、同じ会話を続ける練習方法を見つけたとのことだった。その方法は、なんと私がイギリスで英語を練習した方法と同じだった。父は、いつも私に「ゆっくり話せ、大切な時ほど、ゆっくり話せ」と言っていたのを思いだした。
また、私の名前(国与士)を考えた時に、父の実父から「そんな大そうな名前をつけるものではない」と怒られたそうだ。祖父からは本当にかわいがってもらった、歴史を振り返って知る限り、私は直系長男で期待も大きかったし、一緒に住んでいて、たくさん可愛がってもらった。父は、(父には)厳しい祖父に対して一言、「この名前で行く」と言ったそうだ。幼少の頃から、「お前はお国に与える武士、国与士だ」、「先祖、加世田武五郎は薩摩隼人、島津斉彬公にお仕えした」、「努力を惜しまず、自らの価値を高めて、国の為にしっかり働け」と言われてきた。当時から、そして今も「良い名前ですね」と言われる。「くによし」という名前は聞くが、「国与士」と書くのを見たことはない、とても気に入っている名前だ。戦争後、国の状況が変わっていく中で、「お国のために」という意味の名前をつけることは難しかったと思われるが、私はこの名前がとても好きで誇りに思っている。
そういう話を父の前で繰り返した。そして、子どもの頃にお世話になった叔父さん(父の弟)から、「お兄さんは本当に立派な人です」、そして、「お兄さんがいない今、貴方が当主です。私たちは家来です。喪主のあなたは大切な明日(葬儀)があるから、休んでください」と言われた。叔母からは、「あんたは喪主なんやから、寝んさい」と、何度も言われるので、2時間だけ休ませてもらった。その間も、年老いて、歩くのもままならない叔父さんと叔母さんが父の傍にいれくれた。東京、広島から来てくれただけでもありがたいのに、本当に頭が上がらなかった。ただ、その想いには応えなくてはならないので、睡眠薬を飲んで休ませてもらった。
葬儀の日、さらに他の親族、知人も駆けつけてくれた。父との最後の食事、最後の晩餐に始まり、この日も子どもが和ませてくれた。しかし、だんだんと父との別れが近づいてきて、時間が止まって欲しい想いで一杯だった。一人ひとり最後のお別れの言葉、父は生まれて初めて盛沢山の花で満たされた。狩猟、童謡、戦艦などの趣味の本、釣り竿、カウボーイハット、想い出の写真、そして、私はこれからも世の為に頑張り抜くことを誓い、最近の業績が書かれた新聞や雑誌を父に持たせた。「お父さん、これからもしっかり頑張るので安心してください」、棺桶はゆっくりと閉じられた。その最後の最後まで、父に触れていた。霊きゅう車で火葬場へ。そして、遂に父が暗闇に消えていった。
親族で会食、時間の流れが早く感じた。そうして、火葬が終了したという聞きたくない連絡が入った。重い腰をあげて、ゆっくりゆっくりと父のもとに向かった。そして、変わり果てた父の姿に、またしても全身の力が抜けて砕けてしまいそうだった。我が身が消えようとも、大きくて立派な頭蓋骨と大腿骨は、父の威厳を象徴しているように思えた。喉ぼとけの一部は破損しており、時折おちゃめな父を見るようでもあった。最後まで父らしい。
お遺骨を葬儀場に持ち帰り、そのまま初七日。皆、最後まで父との別れを惜しんでくれた。お通夜、葬儀、初七日では、悲しみと脱力感で、喪主としての役割を果たせなかった。ただ、親戚一同、従妹ら、もちろん、式場の方にも助けてもらって無事に終えることができた。感謝の気持ちでいっぱいだ。久しぶりに会った成長した従妹たち、年老いたおばさん、おじさん達全員と思いっきりハグをして、再会を誓って見送った。
父は快晴、桜が満開の中、愛する人たちに見送られて旅立っていった。父が庭に植えた桜も満開。映画、「ラストサムライ」では、勝元役の渡辺謙が、桜が散っていく中で最後を迎える際に「Perfect」と言って去ったが、父は桜が満開を迎える勢いの中で去って行った。7年前に唄った「わが夢を 捨ててたまるか 若櫻」と言わんばかりに。いつまでもいつまでも勢いに満ちた「若櫻」、夢と希望、ロマンに溢れる加世田勲の新しい挑戦が始まった。
「本日快晴、桜満開、みなさま桜を楽しんで楽しくお元気にお過ごしください」
「またお会いしましょう」
と言ったに違いない。
毎年桜を見るたびに、偉大な父のことを思い出すに違いない。
最後の最後まで努力をするが、潔良さも父らしい、人生の最後だった。
父の想い、父が築いたものはしっかり受けついていくつもりだ。仕事でも、科学と教育の分野で父の魂を次世代につなげていく。2人の子どもはもちろんのこと、10人の甥と姪、8人の孫たちにも父の魂は受け継がれいく。
妹と私の家族は、実家に戻り、母と食事をした。家の片付け、各種手続きで役場を往復するなどして、一人残された母のことを案じながら7泊して大分に戻った。実は、帰省中にも、上述の取材の様子が大分県内で放送されたニュース動画を生徒の保護者が送ってくれていた。ほんの2分あまりの番組だったが、じっくり見ることはできなかった。翌週4月9日に、テレビ局の方から、そのYouTube動画が配信されたという連絡を受けていました。11日に気づいて確認してみると、再生回数が2万回を超えていて驚いた。父が「最後までやり切れ」と言うに違いなく、折れたボロボロの心で受けた取材、生徒の頑張り、そして番組スタッフの方々のお陰で、素晴らしい番組に出来上がっていた。その後も、どんどん再生回数があがり、1週間後の4月16日には再生回数50万回を超え、父の誕生日である本日4月19日には61万回に達している。父は天国への階段を上っている中でも、応援してくれているように思えて仕方がない。
父の旅立に関して、不思議なことがたくさんあった。脳死の状態で、私たちの呼びかけに応じて涙を見せてくれたり、首を振ったり。服薬の副作用で口に入れるもの全てが苦く感じる母は、食事が苦痛と思えるほどの生活を送っているが、父が旅立ってからは、苦みを感じなくなった。さらに、父とともに「歌声サロン」と称したボランティアでアシスタント役だった母の耳に、代わる代わる異なる動揺が流れ込んできている。父の魂は生きている。科学者である私は、通常このような話を信じようとしないが、今回ばかりは、この身をもった体験で、父の魂を信じるほかない。
退職後、小学校でのボランティアでも、丸しかつけない「丸付け先生」として、良い所を見つけて成功させて伸ばす教育で、子ども達の人気を集めた。どんな小さな成功でも「やればできるじゃないか、君たちは」と笑顔で喜んでくれた父。清廉潔白、コツコツ淡々と、堂々と生きて、潔く去った父に、大きな花丸と「やっぱり凄いな、お父さんは」と伝えたい。
一途で真っすぐ、厳しくて優しくて、強くて包容力があるお父さん
緑色のジャンパーにオレンジ色のキャップで目標に向かってコツコツ努力している姿は忘れません。
【父が残した言葉】
「知は脳に 苦は腹に修め 心の糧として 我が身をみがけ」
「歩み過ぎたる人生は 休まずゆっくりこつこつと」
「まず今のことを考える あとのことはその時に考えよう この先、時間は十分にあるのだ なんとワクワクする人生なるや」
「わが夢を 捨ててたまるか 若櫻」
「人生は試練の繰り返しであるが、それを如何に乗り越えるかで 人の価値は決まる」
【父の口癖】
子どもの頃に言われたこと「なんでも一番になれ」、「挑戦しろ」、「おー、それは凄いなぁ」
誰かが成功したとき 「やればできるじゃないか、君たちは」
周囲がもめているとき 「がったんがったん言うな」(「ガタガタ」のまろやかな言い回し)
励ましてくれるとき 「お前もしっかりやれよ」
【父の代名詞】
夢、ロマン、挑戦
私たち残されたものは、たった一人であんなに高い石垣を作ることはできない、立派なログハウスを作ることもできない、猟をすることも30頭の犬を飼うことも、ハーモニカで人を魅了することもできない。ただ、それでも、。父の想いを受けついで、山、海、空、医療、科学、教育、その他、各々の分野で活躍し、社会に貢献している。限界まで自分の能力を高めて世の為人の為に頑張っている。だから、お父さん、安心してください。本当にありがとう。
本日、4月19日はお父さんの誕生日ですね。86回目の誕生日、おめでとう!
大好きなお父さん、世界一尊敬するお父さん、本当に本当にありがとう。
お父さんとお母さんの子どもに生まれて本当に幸せです。天国でまた会いましょう。たくさんのお土産話を持っていくので、待ってて下さい。そして、またお父さんとお母さんの子どもにしてください。母は言った「人生は圧倒言う間」、「椅子に座っている間に終わるよう」という言葉を重く感じた。
我が家のラストサムライ、世界一尊敬するお父さん
思量院釋浄勲 加世田勲様
不器用だけど、お国に与えられた武士の心を持つ国与士より
追記 父の頑張り、家族、親族のサポート、介護のご支援をいただいた方々に感謝します。また、いつか必ず別れの日がきます。父にとっても家族にとっても一番安らかな状態でのお別れの瞬間を作っていただいた主治医はじめ病院スタッフの皆様に感謝いたします。皆様へのご恩を忘れず、日々精進してまいります。そして、最後まで読んでいただいた皆様にも、心より感謝いたします。新型コロナとの戦いはまだ終わっていません。インフルエンザや風邪にも油断できません。高齢者、基礎疾患をお持ちの方はくれぐれもお気をつけてください。