負けない研究開発 Part2
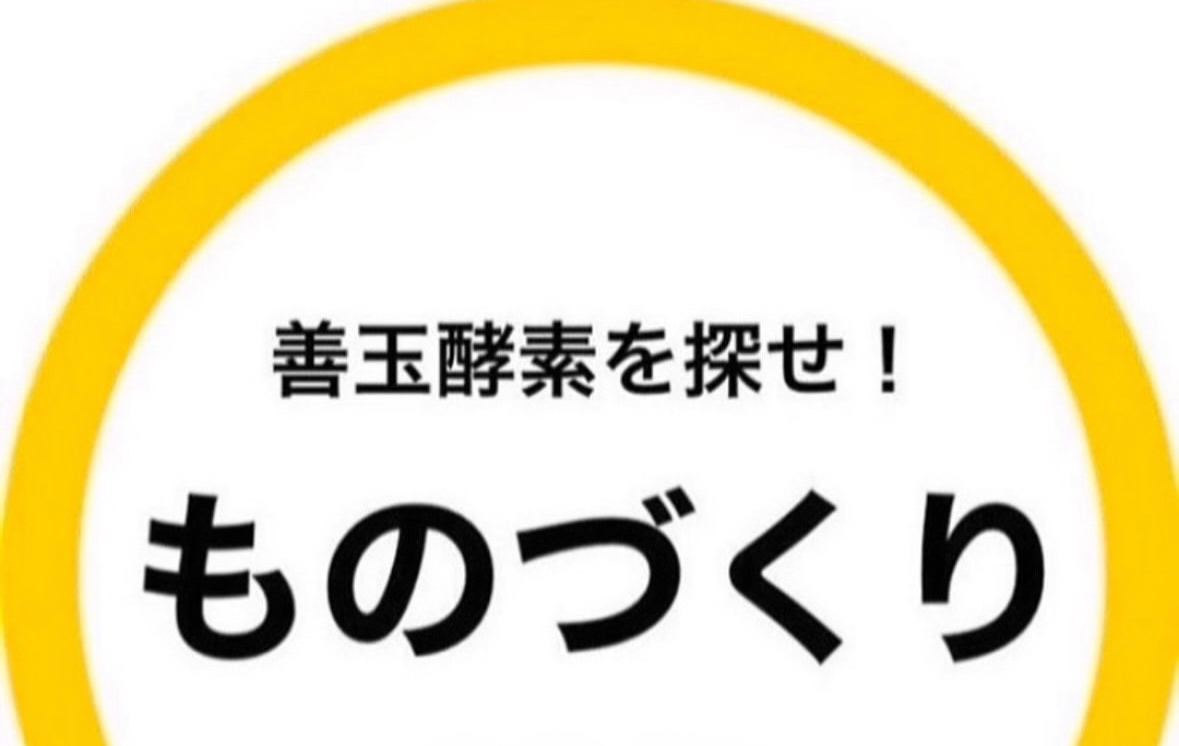
中小企業の負けない研究開発戦略 Part2
研究活動に踏み切ったからといって、すぐに成果が出るとは限りません。
もし簡単に結果が出るものなら、誰でも成功し、皆が横一線になってしまいます。
難しいからこそ、やりがいがあり、差別化にもつながるのです。
だから私は、はじめから一気に深掘りするのではなく、まずは予備実験を重ねながら方向性を見極めていくようにしています。
いくつかの仮説を立て、異なる出口の可能性を探ること。
プロジェクトを柔軟に走らせることで、リスクを抑えつつ、道が開けていく感覚があります。
たとえ途中で行き詰まったとしても、それで終わりではありません。
一度「保留」にしておくのも選択肢のひとつです。
最善を尽くして取り組んだ研究は、いつか別の場所で思いがけないつながりを生み、ブレイクスルーをもたらしてくれることがあります。
私が特に意識しているのは、「一つの実験で、どれだけ多くの、正確な情報を得られるか」。
統計的有意性や再現性はもちろんですが、ポジティブ/ネガティブコントロールの設計や、「おまけ実験」と呼ばれる小さな工夫によって、研究の効率と質は格段に変わります。
また、仮説と異なる結果が出たときこそ、大事なチャンスだと思っています。
「なぜ違ったのか?」「別の角度から見れば新しい可能性があるのでは?」
そう考えることで、可能性の芽を摘まずに、研究の幅がぐっと広がります。
実験に集中していると、つい視野が狭くなりがちです。
だからこそ、自分がいま何をしていて、それが全体の中でどこにつながっているのかを、一度俯瞰して見るよう心がけています。
大きな地図の中に自分の研究を位置づけられたとき、リスクマネジメントもしやすくなり、時間をより有効に使えるようになります。
そして、研究者が道に迷いそうなとき、環境を整え、必要なタイミングで手を差し伸べること。
それが上司の大切な役目だと感じています。
時間はかかるかもしれませんが、良好な関係を築くことができれば、小さな研究室でも仲間と支え合いながら確実に前へ進んでいけるはずです。
最後に、いつも自分に言い聞かせていることを。
「成果は部下のもの、責任は上司がとる」。
この言葉を忘れずに、研究とチームに向き合っていきたいと思っています。
#うちらぼ#科学#研究#成果#差別化#成功チャンス#チーム#ものづくり